
時刻は16時 こちら早町放送社
早町集落を見下ろしつつ下る。西行。1543。
上のような道です。勝連屋敷のある白水はなぜかまとまった集落のない平地。
ところで早町-白水-嘉鈍、この三つの地名をキチンと読める人ってどれだけいるんでしょう?

【正解】しらみどぅ、そーまち、はどぅん
さて車道へ出ました。1548、早町放送社──って、大きく出たな。でも「配達中」の札がかかってる。
西行。

何と?この町名は「そーまち」と読むんだって。そーなんだ。
──と、ワシもこの時知りました。これ以降、バス停の読みがな写真増えるのは、そういうことなのでご勘弁。

所で、この時の目的地・勝連屋敷のことですけど──
興味深いけれど、史料又は考古学的な根拠は特になく、まあ拝所の一つと捉えてよい。喜界町誌に記述があるのが、唯一の典拠。
15世紀の中葉、琉球領内において勢力があった勝連の勢力が喜界島に進出していて この屋敷に勝連親方が住んでいたと伝わっています。勝連親方の「親方」とは琉球王国 の位階のことだそうです。屋敷内に力石と称する二個の石がありますが琉球三山時代に 勝連の殿様が城を築いた際、喜界島民に夫役が課され全島の若者を集めてこの石を持ち上げさせて 体力を試し夫役の人夫として使えるか判断したという由来があるそうです。
※『喜界町誌』より〔後掲喜界島ナビ/勝連屋敷跡〕
勝連屋敷とお隣の保食神社
1554、勝連屋敷跡。
「勝連家
前殿内」
と書かれた石があるだけ?
でもこのL字構造(後日注∶ヒンプン)は,つまり裏に大切なものがあるということで……。

てもここは本当に……物理的に入れない。足の踏み場がない。
この正面の石垣もその先のも、漆喰かコンクリートで補修してある。だから誰かが維持していることは確かです。でも、ここに何かがあった、ということしか分からない。

そこでお隣、保食神社(白水)へ。この発音はバス停表示によると何と「しらみどぅ」。
左手に白水地区公民館と同じ敷地面上です。ということは……おそらく築年は新しい。

いや?上の祠は大理石っぽい新しいものだけど、基盤の岩だけが古い。その間の隙間から、蟻が古石の中の何物かに出入りしております。
つまり、区画整理か何かの際に筆地の中に飲み込んで、古い台座上に新しい祠を建てた可能性があります。
あと、戸口右側の「奉寄進」とのみ読める灯籠はおそらくかなり古い。ここの宮子さんの感覚がよく分からないけれど──維持を優先したんでしょうか。

もう一点。ここは、先の勝連屋敷の敷地の西すぐ脇です。
沖縄及び日本神道的な感覚なら、二つの拝所は古い方の中に合祀するのが普通に思えます。
あえて外に、でも隣接して造った──というのは、何かの意志が働いたのでしょうか。
1612、退去。

道路より左手は畑、右手は集落という景観が続く。
つまり、地形利用の色分けが明確過ぎる。
古くからの道のラインでしょうか?海岸線とも思えないけれど……。
蘇鉄大爆発

西後方には、百之台から城久遺跡方面に連なる高地が顔を見せてます。この嘉鈍から浦原までの4kmが、崖下に伸びる喜界島の東海岸になります。

何ということもない集落、に見えます。現地読みは「はどぅん」という。
琉球王国時代のミヤの跡があり、ミヤから山手を上の道(うぃんのじょう)、海側を下の道(しゃんのじょう)と称する。元禄五年(一六九二)の喜界島帳留(列朝制度)に東間切与人の噯として「嘉鉄村」とみえるのは嘉鈍の誤記であろう。天保一〇年(一八三九)に「嘉鈍村」の西則が砂糖一万斤を上納した功によって与人となった。墓が当地の墓地にある。向井家の祖清風は近世に琉球から竜舌蘭を持帰り、島内に植えさせたという。〔日本歴史地名大系 「嘉鈍村」←コトバンク/嘉鈍村(読み)はどぅんむら〕
──酷く興味深い記述ばかりだけど、全く手が出ない。類推も見当もつきません。

嘉純集落へ入る。1621。
で、ここの目的地は観光地でして──巨大ソテツ(→GM.)。樹齢3百年。拝みの跡はない。町指定天然記念物。というかもうソテツに見えません、何かが爆発してるって感じです。

神サマばかりの夕焼け道

嘉純の山手から海方向を一枚。やはり集落内側ラインの微妙なクッキリ感が腑に落ちません。

保食神社。畑地の真ん中の長い参道。
末吉神社。異様に低い鳥居と薄暗い社林の昏い社。
で──あれ?神サマばかりで集落がないぞ?

ダメだ。
体力的に、今から夜にかけて湾まで走り切る自信がないし、それは勿体ないし──と阿伝(あでぃん)からバスを使うことにします。全然予定になかった行動ですけど……。
明日はバスでこの地点へ戻り、再度走ろう。
阿伝で待ちながら

バス停表示は──ない。
無いけれど、おそらく別の道ということはない。東北行きバス停(らしき場所)の対面で待てばいいんでしょう。

ここの海岸は、粗い。
岩のだらけで上に草が生えてるけれど、侵食もされてない。
遠方の公園で遊ぶ子どもの声だけが、潮騒に混ざり聴こえてくる。
通過時刻1712まで……あと14分。
沖縄からしても奄美からしても、その名の通りの奇怪な島です。
中央部の尾根を振り返る。東海岸から見ると……切り立つような険しさです。向こうに高地があるようには、とても見えない。この尾根を利用する限り、確かに城久地域の防御力は強力だったでしょう。
今日はそれを足で理解できました。
1715、3分遅れた。でもバスには乗れました。
運ちゃんは、アロハシャツのお兄ちゃん。客は一人のみ。スピードは……酷くゆっくり安全運転です。
整理券も料金表示もない。仕方ないから口で訊くと──三百円とのこと。額がきっちりしてるからおそらく一律定額。もちろんアナウンスもないから集落名が分からない。位置情報をオンにしてGM.を見ると──しめた!内陸じゃなく西海岸を行くらしい。明日のルート視察が出来そうです。
◯Aバスで行こう!

町立あゆみ幼稚園。
この先が手久津久です。いつの間にかあれだけ聳えてた丘陵が低くなってる。
朝戸神社はバス道からは見えないらしい。
荒木ではバスが集落内へ。保食神社も隠れてる。喜界島の宗教地は通りからは見えないのが通例らしい。
湾に帰着。1739、ファミリーショップよしかわ前で下車。
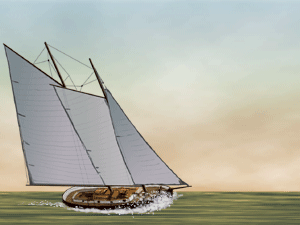
ドラッグストア・ホーユーには、なかなか見つからなかった分包の入浴剤がありました!日本酒風呂とか変なのだけど……まああれば良い!
十兵衛は、夜は予約オンリーになってしまってました。山羊汁食べれんよ〜。

そこで1836。本日もAcoopへ行った帰り、湾の港をよく見る。砂浜があり、やはり岩礁が多い。現在の港湾はその沖を埋め立てて使っている。
つまり喜界島には現代の大型船舶に使いやすいような良港がない。小船用なんだけど、小船では外からは直接来れない。

■レポ:喜界島の琉球神道色はなぜ薄いか?
奄美地方は、薩摩の直接支配を受けた分、むしろ古色を濃く残している部分がある、と言われる面かあります。琉球に支配された被害者感覚を持つ奄美の文化なので、それを「古琉球」と呼ぶのはやや抵抗感がありますから、それを何と呼ぶべきかはよく分からない。
ただ、少なくとも喜界島で、そういう「古色」はあまり濃密ではありませんでした。この点を語る、喜界町誌の引用を挙げてみます。
奄美諸島の統治が薩摩藩に移るにおよんで,藩がノロの祭祀や行事に制限を加えたり,奄美の村々にヤマト式の社寺を勧請したりしたので,琉球古来の神道は次第に衰退の一途を辿り今日に至ったのてある。〔後掲喜界町誌(以下「町誌」という。)〕
喜界町誌著者は、具体の事象としてノロとそれを巡る信仰について挙げています。
大島の場合(略)地域によっては現在でも,ノロの祭りのためのアシャゲやトネヤが保存され,祭りも地域の恒例行事として,古式ゆかしく伝承されているという。
それに比べて喜界島の場合は,ノロ信仰は遠い過去のものとなり,ミヤ跡や神山などの遺跡を通して,わずかに往時が偲ばれるだけである。いったい指呼の間にある喜界島と大島で,それほどノロの信仰に差異が見られるのはどうしてだろうか。〔後掲町誌〕
大島-喜界島の格差説
町誌は「大島は山岳地帯が多」くて外部と途絶された地域があったから、という点を第一の理由に挙げます。けれど、これは日本の山岳部を考えると絶対条件たり得ないし、またその実証的証拠もよく考えればありません。
また第二点として、大島の神女組が二教区制でライバル意識を持ったため、とするけれど、これもまた同様に説得力を欠く。そんな政治色が文化を興隆させる、という図式はいかにも安直です。
ただ、これらの記述の中で触れている次の二点は、効力を持つ可能性があると思えました。
(喜界島は)神女組織も大島の上方に所属していたものと思われ、大阿母も大島上方との兼務で、五間切(藩政時代は六間切)のノロたちにも対抗意識はなく、その活動も大島ほどではなかったものと思われる。また、奄美五島の中で琉球王朝に支配されていた期間が最も短いのも喜界島である。〔後掲町誌〕
つまり、経緯や理由はともかく、宗教的な独立性を早い時期に失ったらしい。
なお、琉球王朝支配期間が短い、というのは奄美の宗教的独立性が琉球王国による支配への抵抗感覚に共鳴したものだったとする立場からのようです。ナイチャーの我々からは逆に思えますけど──
(喜界島の)神社のほとんどは藩政時代に、地元の有力者たちによって勧請されたものであるが、代官所は主な神社の例祭には祭米を支給して、神社神道を保護奨励してきた。ちなみにこれらの神社のおおかたの宮司役は、他ならぬノロやユタと言われる神女たちであった。〔後掲町誌〕
これも事実なら、他の琉球弧ではちょっと考えにくい事態です。つまり琉球神道から日本神道への「転職」が、かなり融通無碍に行われた、ということです。
加えて、薩摩の代官所による神道優遇補助金が出たことが記されてます。薩摩の懐柔策が、喜界島については特に手厚かった、と捉えることもできるデータです。
喜界島の他の事象以上に、この点は全く見通しが立ちません。





