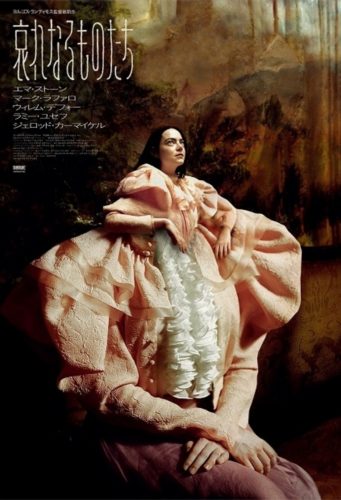目録
ノッポ椰子 マジックアワーまで少し


芭蕉林 名幸祠の獅子睨む
場所の目安通りに進むと──すぐに見つかりました。何で前回気にならなかったのか?いや、これは沖縄の聖地によくあることで、気付くまですぐ傍を通り過ぎてることはよくあります。
1440、名幸祠。
〔日本名〕名護城公園
〔沖縄名〕なこうじ〔後掲JINさん〕
〔米軍名〕-

不規則な形の平坦地。
入口には建売住宅のような門。
左手手前と右手半ばにそれぞれ拝壇。右手正面に碑文。
少し左手奥に祠。これを対のシーサー及び灯籠が護ってます。

右手拝壇へ。1444。
いずれもウチカビなどの跡なし。
碑文は読めないけれど──題名は「名幸祠由緒」と記されてるらしい。

祠はコンクリート製。供物はないけど、最低限の手入れはしてある雰囲気。
灯籠には「奉納」の二字が読めます。
破れた金網の中には壷やガラス瓶。これらは整然と並んでます。その奥にはもうイビは見当たりません。

帰路に気づく。
入口から右手すぐのやや小高い場所があり、ガジュマルが聳えてます。この根元、先の祠側に拝所がありました。

想像を逞しくすると──これが本来の拝所で、後に(おそらく名護城が神社になった戦前の軍国時代に)神社様式をとるために後方の「境内の樹木」になったのではないでしょうか?
イジグチ屋 祠の奥の石たたき

1458、下へ。
イジグチ屋。
これもコンクリート、横にはガラス窓のある祠。入ってやや右にズレた正面に三段の祭壇。花と茶碗が据えてある。

一礼、祠を覗く。
名幸祠と同じく左手に石が2つ。こちらが本来の沖縄のものでしょう。
なぜイジグチだけが、名護神社に取り込まれなかったのかは分かりませんけど。

祠の奥にも背後にイビはないようです。けれど、大きな樹木が後ろからのしかかるように伸びています。
なお、イジグチの語義は見当もつきません。

退去。
雨は何とか持ってます。いつ降ってもすぐさま宿へ帰る態勢でいたんですけど──それなら飯食っちゃいますか?

沖縄は爽秋 豚足はスイーツ
帰路ぶらり、というルートで通りかかってみると……開いてるの?
路地奥なので、我ながらよく見つけれたと思う。というか、よく閉まってると勘違いしなかったと思う。
1519(名護市大東1丁目9)新山そば
てびちそば450

那覇の「大東そば」とは、大東島じゃなく名護の大東なのか?※面白い発想たけど、やっぱり調べる限り「大東そば」とは大東諸島の風味が濃く、素朴な味わいで、麺のモチモチ感が強いものを言います。〔後掲Lemon8〕
そばの味がまさにあの(名護大東の)図太い味でした。一方で、浙江の拉麺のような、小麦の香る豊かな香。
さらにこのてびちは……トロトロを通り越して、口の中でゼリーのように溶けていきます。このてびちは、最早スイーツです。


何てこった!「パイ工房おしゃれ」も開いてました!この店は、その後の経験上も、2回のうち1回は閉まってるのに──
で、その帰り道。屋部川に沿ってホテルに帰ろうとしたら……
GM.(経路)
屋部川の南岸の丘が、気になった。
公園状にしてあるけれど、沖縄本島での公園はかなりの確率で偽装、というのはこれまで学んできてます。これも御嶽ではないか?

〔日本名〕名護市宇茂佐の森五丁目
〔沖縄名〕ななしきむい・ぷーみちゃー
〔米軍名〕-
台風なので登らない丘二つ
1557。見つけた案内板には凄いことが書いてありました。
今でこそ河川整備や区画整理などにより,畑地や宅地に利用されるようになったこの付近も,かつては屋部川の流域に発達した広大な湿地帯であった。満潮時にはさらに上流まで潮がさし,そこに点在した丘(ムイ)は,まるで湖水に浮かぶ島のようであったという。プーミチャーは崖壁に,七月森は山頂の岩陰に墓があり,そこを屋部大一門(プーイチムン)では先祖の墓として拝んでいる。
屋部大一門では毎年旧暦の11月吉日に,ここで「ぷうみちゃ拝み」を行い,卯・未・亥年には一門中で買った牛を墓前でつぶして先祖に供え,共食する「牛焼き」が行われる。(続)

(続)「牛焼き」前日の晩,大一門の宗家の一つである「あじみち」の神屋(はみやー)の前に牛がくくられ,当日の早朝,神屋の前で7回引き回された後,プーミチャーに向かう。プーミチャーの墓前で「今日が牛焼きの日である」ことを告げ,大一門の男たちの手で牛が解体され,ゆでた肉(シルベーシ)や牛汁が準備される。午後になると,屋部を中心に各地に広がった大一門の方々が拝みに訪れ,汁を食べ,肉を土産に交流を深める。(略)他の地域に見られる「牛焼き」は,ムラに入る悪風などを防ぐために行うムラの祭りであるが,この行事は一門の繁栄と交流を目的とする一門の祭りである。〔緑のネットワーク広場施設案内図/ふうみちゃ拝み─屋部大一門の牛焼き行事─〕

すると──?
この先の公園内墓地の十字路を、右に行った先の丘。これが
名護城が栄えていた時代 ナナシキムイのある宇茂佐プーミチャー(大神原)には 北山にゆかりのある人々等が住み集落を形成していた。宇茂佐古島遺跡からは 主に十五世紀から十七世紀頃の生活の跡が発掘されている。兵乱が止み 太平の世が訪れると 宇茂佐プーミチャーの人々も現在の宇茂佐・屋部等に移っていったという。
ナナシキムイの頂上には 岩壁を塞いだ墓があり 仲北山にゆかりのある「崎山按司」も祀られていると伝える「屋部大一門」では毎年 旧暦十一月の「プーミチャー拝み」祭事に 先祖の眠るこの墓を拝んでいる。(続)

(続) ナナシキムイ(七月森)の由来は「昔この山は 富士山よりも高くそびえ頂上にたどり着くには七ヶ月もかかった。ただあまりにも細長く高い山であったため ポキッと折れてしまった。ナナシキムイはその山の根っこにあたる」という昔話が伝えられる。〔「ナナシキムイの碑」案内文,平成23年3月宇茂佐区 屋部大一門〕
登ろうかとうか迷ってると──風がびゅんびゅん吹いてきました。
台風と言えば台風です。
北山の落人が身を寄せ合ってきた丘、と思われます。少しは北山の各所を歩いた身としては、どうにも興味本位に立ち入る気がしない。
一礼して辞す。台風ですしね。
林檎ホリックはパイ工房おしゃれ

我部祖河食堂の後寄ってみた「ベーグル ミスリ」は既に閉まってました。
「一番人気の黒糖が残ってて良かったですね」とお姉さんに言われたけど……ワシが買った後はそれ一つになってたはず。売れ残ってたんじゃね?とは言わずに笑って合わせてましたけど。

さて明日から(朝には雨風が収まる,という予報が正しいとすれば)です。
──今日、クバ御嶽に備えて虫除けスプレーまで買ったんですけど…………七月森の空気を吸って、止めようと思い始めました。地元の人が世界遺産になって無神経な観光客に困り果ててる最高聖地は、地元の人に独占して頂くべきです。
北山では、そういうインディジョーンズ的な侵入者姿勢ではなくて、今帰仁の普通のムラの普通の信仰生活を、細かく字を回ってみていくことにします。
それで今帰仁の生活感覚──広義の「文化」が把握されて……いけばお慰みですけどね。

「おしゃれ工房」はアルミケースに種類別に並んだミニパイをナイロン袋に取っていき、レジに持って行って個数×単価で支払う形式。
日本によくあるふわふわデニッシュ生地ではなく、耳の部分などはほとんどクッキー。アメリカンタイプのパイを、アメリカには絶対にないミニサイズにしてる,アメリカ的にはナンセンスな代物ながら、うちなんちゅ的には大変購入しやすい、ほどよくちゃんぷるーしてある商品なのです。
売れ筋との表示もあるだけあって、アップルが絶品。嫌いな人からすると「……腐ってんじゃね?」という感じのドロドロにくすんだ飴色のアンなんですけど──林檎ホリックの人にはこれが堪らんのだよ!わははは。

■レポ:名護に海陸人が対峙した季
七月森の話は笑い話風にこんな風にも語られています。
ある人が大和に行って富士山を見て、「この山も高いが、沖縄にはもっと高い山がある」といった。
大和の人が「どんな山だ」と聞くと、「登るのに七カ月もかかるから七月森と呼んでいる」といった。
大和の人はぜひ見せてくれといい沖縄にきた。案内して見せると、どこにも高い山はない。「高い山なんかないじゃないか」というと、「実はこの前の地震で折れてしまった。ほら、ここが根元で次がそこ、その次が向こう」と説明した。
見ると、小さな山が並んで点々とあった。
それを見て大和の人は納得したという。
〔後掲名護大百科事典/富士山より高い七月森 ※出典:「わがまちわがむら」 (昭和56年民話調査より)〕
──何で納得すんねん!とツッコまずにはおれない無茶苦茶な小話ですけど、2点、参照できることがあります。
一つは、古・名護人が富士山を見に行き、その富士遊行に付き合った大和んちゅが、名護まで来る──という話がそれほど珍しさもない感覚で語られること。
もう一つは、「登るのに七カ月もかかる」山が「起き上がりこぼし」状になった程、名護湾が小島を散らばせたような原風景を持つことてす。

うんさの森 ウイヌハーナカヌハーシチャヌハー
七月森の南北の広いエリアが、住所表示「宇茂佐」又は「宇茂佐の森」と呼ばれています。
方言ではウンサという。沖縄本島北部の本部(もとぶ)半島基部,名護湾の北岸に位置する。西隣の屋部と併称され,関係が深い。西部に標高30m以下の琉球石灰岩の丘陵ウンサムイがあり,その西麓の小字古島原は屋部・宇茂佐の古島と伝え,ウイヌハー・ナカヌハー・シチャヌハーと呼ばれる拝泉がある。古島に住んでいた7軒のうち6軒が屋部の始祖となり,1軒が宇茂佐の始祖となったという。古島は,グスク時代から近世にかけての遺跡で,付近では高麗瓦が出土している。そのほか,沖縄考古編年後期~グスク時代の遺跡が小字東兼久原にある。〔角川日本地名大辞典/宇茂佐【うむさ】〕
七月森から南1km強、屋部川河口部には数多くの遺跡が見つかってますけど、前掲引用の末尾に記載する、最も特筆すべきものに宇茂佐古島遺跡があります。

まず、この河口側には船着を連想させる地名が多い。
③シンドゥガニク 船頭兼久
⑧シキジン 船着場∶山原船などが荷を積み下ろした場所〔後掲名護市教委 図3凡例〕

──正直、水深からすると中国からの外航船が入って来れるような水深ではありませんけど、(⑧シキジン記述中にある)船底が浅かったと言われる山原船なら可能だったのでしょうか。
(参考)現時点での山原船諸元推測
工学的な観点からすると非常に合理的なものであり,沖縄における造船技術の発展ととらえることもできる.
マーラン船の性能については,琉球史料によれば馬艦船は航海が安全で船足が速いと評価されており(喜捨場,1974) 現代技術の観点から評価することは意義のあることであろう.しかし,マーラン船の船型については,建造地域や,船大工によりそれぞれ工夫がされたとされ,各種の形状がありうるものといえる.また,図面等の概要が発表されているものの(沖縄県文化財調査報告書第101集,1991),船型の数値的検討の面からは必ずしも十分とはいえない.従って,船製形状を厳密に再現できるまで詳細な数量化は,船型を復元するための目的にとどまらず,マーラン船の特性を定量的に評価するために必要な要素と考えられる.
なお,参考までに琉球へ伝来した造船技術のもととなる進貢船についてその船体形状の特徴を述べると,竜骨を有し,船首部に托浪板,横隔壁を有することがあげられる.水面下の船体形状は尖頭型ではなく輔広い水線形状を有しており,側面の水線酉形状は緩やかな曲線で構成されている.また,舵の保持は舵下端部をロープで船首前方に引き船首部に設けた画定材に閤縛する形式である.」〔後掲八木〕
※原注 坂井英伸:「マーラン船の多様化とその背景J,民具マンスリ一第35巻第 5号, 2002年 8月.
喜舎場一際:「マーラン船」考,海事史研究第23号, 1974年10月, pp.31-57.
沖縄県文化財課査報告書第101集,西表島船浦スラ所跡一港湾施設工事等に伴う発掘調査 ,沖縄県教育委員会, 1991
年 3月, pp.63-66.



沖縄考古学の「高麗系瓦」
前掲引用の「高麗瓦が出土」したというのは、従来から屋部川の河口で発見されていたものが、宇茂佐古島遺跡でも「ほらやっぱりみつかった」ということだったようです。
平成7~9(1995~1997)に宇茂佐第二土地区画整理事業に伴い実施された緊急発掘調査において、14~17世紀頃に生産された陶磁器類を主体に、古銭、石器、高麗系古瓦や煙管など多彩な遺物が出土しています。
陶磁器は、沖縄製陶器、中国製の青磁、白磁、青花が出土しており、タイやベトナムのものと考えられる陶磁器も少量ながら出土しています。また、日本製の肥前陶磁器や備前焼などは16世紀後半以降の生産年代であり、総じて16世紀以降、17・18世紀頃までの焼物が出土してます。
特筆すべき遺物としては、高麗系の古瓦が多く出土したことがあげられます。県内の高麗系古瓦の生産年代は14世紀後半~15世紀前半頃と考えられていますが、その正確な生産年代や生産地について明らかになっていません。
本遺跡の側を流れる屋部川の河口でこの瓦が採集されることは、研究者の間ではたびたび注目されて来ました(屋部川河口古瓦出土地)。この調査において、その理由を明らかにすることはできませんでしたが、この瓦が多く出土したことは、瓦生産地や流通ルートの解明などの観点から、注目されています。〔後掲名護市役所/宇茂佐古島遺跡〕
「高麗系(古)瓦」は沖縄考古学界での慎重な呼び名のようです。「14世紀後半~15世紀前半頃」の朝鮮と言えば──
1392年 李成桂(伝・女真族)高麗王に即位(高麗・恭譲王から王位簒奪)
1419年 世宗(1418-1450在位)対馬遠征(応永の外寇∶倭寇征伐を理由として)
1637年に仁祖が清に降伏(三田渡の降伏∶大清皇帝功徳碑)するまでの高麗の歴史における、最初の「元気旺盛な」一世紀です。あわよくば日本を侵略しようとしたほどですから、1469(成化5)年に一旦滅ぶ第一尚氏の琉球にも……何というか「強気」で流入してきた集団があったのでしょうか。

高麗系瓦とは、浦添城跡や首里城跡を中心に出土する還元焼成炎で焼かれた古瓦を称する。取り分け平瓦は凸面に「癸酉年高麗瓦匠造」、「大天」、「天」銘及び格子状模様の叩き目痕を有するものが特徴とされている。丸瓦は玉縁の付く模骨巻きの二枚割り造りで、両瓦とも凹面から切り込みを入れて。分割する造瓦法でなされている(註1 ) 。
名護市内においては本遺跡と隣接する屋部川河口(註 2)、名護城からの出土が報告されている(註 3)。本遺跡出土の古瓦を上原静氏に見て戴いたところ、軒丸瓦 (鐙瓦)、 軒平瓦(字瓦)、丸瓦 (男瓦)、平瓦(交瓦)、有段式平瓦、役瓦の6種が確認された。〔後掲名護市教委、82枚目p75〕
註 2 多和田真淳 「琉球列島の貝塚分布と編年の概念」『文化財要覧』琉球政府文化財保護委員会 1956
註3 名護グスク 「名護城遺跨を視察」ー沖縄考古学会メンバー一 琉球新報 1990年1月23日
銘や叩き目痕は、技術的なものというより刻銘の性格のものと推測されますから、当時の琉球で、最上位の支配層までが彼らの瓦の流行にハマったのだと思われます。
そういう節操のない「文化的劣位」の相は、アメリカと中国にだけであって、日本や朝鮮に対し
Ⅶ類 (第29図14・15)体部が内湾しながら立ち上がり、見込み及び高台が露胎となる碗である。外体面の文様に注目すると、ベトナムのホイアンから検出された中国の彰州窯系の碗に類似している(註1)。(略)
Ⅺ類 (第30図21 ・22)腰部がやや膨らみ、口縁部が直口あるいは若干外反する福建・広東系の印判手と称されている碗である。〔後掲名護市教委、58枚目p51〕
けれど──前章の許田、また陸人のコアだった名護城の存在を考えると、謎が深まります。唐人が来たのは、なぜ許田や名護城、名護湾東岸ではなくて北岸だったのでしょう?前掲「北山にゆかりのある人々」が本当にここに居り、それが高麗瓦の推定年代(14C後半〜15C前半)とすれば、対明交易が史書に記される怕尼芝(はにし∶交易1383年-)、珉(みん∶交易1395)、攀安知(はんあち∶交易-1416年)の山北三王、かつ伝・三山統一1429年の2〜3世代
それは、政治権力の帰趨はともかく、「みやきせん」経済交易ネットワークは第一尚氏代にはなお健在だった、という可能性を予見させるのです。何よりも、琉球を虎視眈々と狙っていたであろう新興・高麗の瓦技術者集団は、浦添・首里と並び名護に瓦を遺した(→前掲)のですから。

ここが根元でその次が向こう
「登るのに七カ月もかかる」巨峰・七月森が、折れて名護湾に落ちた現在の様は、要するに多島湾です。地質的には国頭層群の嘉陽層と名護層がせめぎ合っている位置で、大げさに言えば嘉陽層の海に突出した名護層の岬の突端が七月森です。──そういう地質的な意味では、七月森は本当に巨峰と言えなくもない。


この地質上で、現在確認される定番の陸人による名護最古拠点・名護城と、伝・最古の、多分海人の拠点である七月森は、名護湾内でこのように対峙しています。


七月森の海人も顧客が必要だったでしょう。名護城からも高麗瓦は出土しています(下図参照)。ただし、第二尚氏三代・尚真王(1477~1526)代の按司集住政策(首里)が図られ、1500年前後に名護城は廃城になったと考えられています。14-15Cの高麗瓦時代の直後になりますから──北山残党と組んで大儲けしてたのが、首里にバレたのかもしれません。

転記データ∶名幸記傳
後掲JINさんの記録によると、名幸祠には「名幸記傳」という記銘が残されているという。多分見落としたのだと思われるので、悔恨も込めて転記しておきます。幾つか未知のデータもありましたし。
西紀二 三百年北山は血族同士が権力を争って乱をおこし、欺きて仲昔北山六代の世主今帰仁城主の系統は亡んで、傍系の怕尼芝が北山に君臨した。
口碑の傳える名幸は滅亡した城主の嫡琉千代松やい、彼はこの騒乱から難を遁れ祭祀眷属を共に一族なる名護按司に寄託亡命し竊に宗廟の恢復を謀つたが成らず雄志空しく病に斃れた。
宗家を奪つた怕尼芝は時に中山の衰頽に乗じて自ら北山王を僭稱し北方の覇者をもつて國頭諸間切を威圧するに至つては後難を怖れる名護按司が先君の世子を庇護隠秘するために■勉苦肉の計を用いたことは推考に難しくない。
世子の名をいわれのない名幸大屋子の假名で糊塗し亥は彼の遺骸を此◯城川の懸崖幽谷に密葬するなど北山王統の虎の子を預る。一説では名幸を名護按司の次子となし十五世紀末按司家が國王尚真の勧告に従つて后を首里府に移した當初の管領◯按司◯とまいす。
古文書に名護は那古につくり名幸は那古の転訛と乃ち名護城の首長那古大屋子とする説もあるが根拠はない。
二九百〇十三年庚子孟夏 北嘉宇太郎 しるす〔銘←後掲JIN〕
この伝によると、山北三代の半ば、怕尼芝の時に
〉〉〉〉〉参考資料
※沖縄の山、川、海を考える懇話会/ビジョン URL:https://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/yamakawaumi/vijon/vijon.htm
沖縄県立博物館・美術館(おきみゅー)/首里城の建物に葺かれていた瓦の色は赤色なのか、灰色なのか | 学芸員コラム
URL:https://okimu.jp/sp/museum/column/1604882797/
JINさんの陽鉢農遠日記 2022/沖縄本島一周の旅へ(その13):【3日目・9/27】名護城跡~白い煙と黒い煙の碑~ひんぷんガジュマル~徳田球一記念碑~宮城與徳の碑~2000年九州・沖縄サミット記念写真 | JINさんの陽蜂農遠日記 – 楽天ブログ
URL:https://plaza.rakuten.co.jp/hitoshisan/diary/202210150000/?scid=wi_blg_amp_diary_next
釣りナビくん(運営∶マリーンネットワークス株式会社) アプリ URL:https://tsurinavi-kun.com/
名護市教育委員会社会教育課 1999 『宇茂佐古島遺跡』名護市文化財調査報告13
※ 全国文化財総覧 URL:https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/142577
名護市役所
/宇茂佐古島遺跡
URL:https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2019032800067/
/ナングシク遺跡群
URL:https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2019032800135/
名護大百科事典 Nagopedia 試行版
/富士山より高い七月森 (宇茂佐の伝承話)
URL:https://sites.google.com/site/nypedia/home/nago_bunkazai/nago_mukasibanasi/umusa_nanasitimui
八木光・河邉寛 2009「沖縄マーラン船の船型に関する調査研究」『東海大学紀要海洋学部』第7巻,第1号. p.1-10
※PDF URL:https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010780400.pdf
(れもん)Lemon8/(投稿を元にAI概要)沖縄そばの特徴と地域ごとの違いまとめ
URL:https://www.lemon8-app.com/experience/%E6%B2%96%E7%B8%84%E3%81%9D%E3%81%B0%E3%81%AE%E7%89%B9%E5%BE%B4%E3%81%A8%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%94%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81?region=jp