※数位人文∶デジタル・ヒューマニティーズの中国語訳。
目録
デジタル・ヒューマニティーズの研究者の多くが目指しているのは、歴史、哲学、文学、宗教学もしくは社会学の研究と教育におけるテキスト分析技術、GIS、コモンズに基づく協働(commons-based peer collaboration)、双方向型ゲーム、マルチメディアの利用など、自身の学術活動に新しい技術を取り入れることである。認識論的に言えば、次の2つの問いを発することにより定義することができる。すなわち、
我々は何となく知っていることをどのようにして知ることができるのか
、そして(リサ・サミュエルズ(Lisa Samuels)の言を引用すれば)、
我々は自身が知らないことをどのように想像することができるのか
。また方法論的に言えば、知識の方法、すなわちその取得、分散、および収集は、一般教養を構成する諸分野に共通したものである、という考えにより定義することができる。ジョン・アンスワース(John Unsworth)はこうした共通の活動を、発見(discovering)、解釈(annotating)、比較(comparing)、参照(referring)、サンプリング(sampling)、説明(illustrating)、および表現(representing)と定義している。ウィラード・マッカーシー(Willard McCarty)は、このような活動のすべてを、
原則としてコンピューターを使ったモデリングにより表すことができ
、こうしたモデリングは(クリフォード・ギアツ(Clifford Geertz)の区別を借りれば)、
既存対象のモデルと、想像される既存対象についてのモデルの間を行き来する
[2]、と主張している。
諸分野の研究者の多くが、
コンピューター利用の最大の効果は人文科学研究のスピードを速めることではなく、文化遺産の研究に長い間横たわる諸問題に取り組むための新しい手法と枠組みをもたらすことである
[2]というロベルト・ブサ(Roberto Busa)神父の主張に賛同している[3]。〔wiki/デジタル・ヒューマニティーズ,2022.7.26現在〕
※[2] McCarty, Willard (2005), Humanities Computing, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
[3] Busa, Roberto. (1980). ‘The Annals of Humanities Computing: The Index Thomisticus’, in Computers and the Humanities 14:83-90.

デジタル・ヒューマニティーズの行く先には何があるのか。
現代のデジタル・ヒューマニティーズは過去に背を向けているのではなく、それに肩の上に立つ形で存在している。それは、たとえリポジトリの構築や編集を超えた新たな統合的実践の方へと移行しようとしているとはいえ、
統計処理(コンピュータを用いた言語学)、
リンク作成(ハイパーテキスト)、
モデリング(建築的で視覚的な表示)、
構造化されたデータの作成 (XML)、
反復的編集や
ヴァージョン管理(分析的で創造的な実践及び校訂版)
という形で過去 70 年にわたってなされてきた先駆的な仕事に敬意を表している。それは、コンピュータを用いた人文学と、デジタル・ヒューマニティーズの黎明期の開拓者たちを活気づけたのと同様の中核的信念に触発されている。その信念とは、コンピュータを用いたツールは人文学の探究の概念、射程、方法論、関心を持つ人々を変容させる潜在的可能性を持っているというものである。〔後掲p9〕
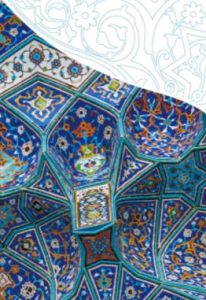
デジタル・ヒューマニティーズは人文学における従来の研究や教育の形式をどのように受け継いでいないか。
ここ6世紀弱の間、人文学における知のモデルは、印刷という知の生産および伝播の基本となる媒体の力によって形作られてきた。デジタル・ヒューマニティーズは印刷という文化を拒絶したり、印刷というモデルをデジタルの枠組みへただ埋め込むのではなく、印刷を超える時代、あるいは印刷以後の時代における知のモデルを生み出そうとしている。デジタル・ヒューマニティーズによって生み出される知のモデルは、知の伝達の仕組みを更新することにとどまるものではなく、人文学の領域における認知および認識の作り直しをも伴うものであり、これは
印刷という側面に関してデジタルの生み出すアフォーダンスの機能
である。デジタル・ヒューマニティーズによって生み出される知のモデルはまた、人文学の研究や教育における共同作業の役割の拡大を重視してもいる。
印刷を超える時代におけるデジタル・ヒューマニティーズの機能とはどのようなものか。
一般に、印刷物がもたらすものとは一方向的な視覚野、線形構造、有限で安定的な特徴をもつ研究成果のアウトプット、書物という物質的形態への配慮を強いられた議論と文書化の規模である。これに対して、印刷を超えるデジタル時代においては、同じ物質に対して複数の視野を切り替えることができる。
滑らかな大きさの移行、
すなわち極大から極小まで「ズーム」ができる
のである。さらには、研究成果のアウトプットに物的資料や覚書きや書簡といったようなデータ一式を織り交ぜることもできる。印刷を超える時代には、画面や拡張現実の空間によって、
コーパスの面取りや
フィルタリングやバージョニング、
単一のリポジトリへのアプローチにおける複数の経路の併存、
複線的な議論の形式
が可能になる。拡張可能だというのは、
無限に大きさを変えられることと、
生産ではなく過程に基づくこと
という二つの意味においてである。書物が印刷されるときは版として固定され、改訂するには再版を要する。これに対してデジタルの生産物は、書き換え可能な基盤のおかげで素早い読込み速度で変更したり改訂したりできる。単一のデジタルの生産物は複数の作者によって、複数のプラットフォームにおいて、複数の道に進むことができる。デジタルの生産物は、「完成」の前後に他人が編集を加えることもできる。〔後掲pp12-13〕
教育機関はデジタル・ヒューマニティーズの研究をどのように支えていくことができるのか?
高等教育機関は人文学の分野において、より失敗を恐れない文化を促進し、助長しなければならない。すなわち、科学における場合と同様に、
革新的で理論的な研究に着手する際には
「失敗」が生産的な成果として受け入れられるような文化
である。生産的な失敗と単なる劣った研究を区別することは、革新が本質的な意義である研究コミュニティを奨励する際に、本質的に重要である。〔後掲p16〕
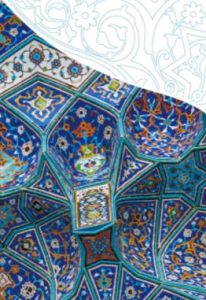
http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/dhc/sg2dh.pdf
この日本語訳は、東京大学大学院人文社会系研究科2012年度「人文情報学概論」(下田正弘・A. Charles Muller・永崎研宣担当)の一環として行われたものです。米国で広まりつつあるDigital Humanitiesの興味深い一面をあらわすものとして、必ずしも正確な訳ではないかもしれませんが、ここに公開することにいたしました。日本語訳参加者は以下の通りです。
中川 友喜/ 長野 壮一/ 柏 達己/ 原木 万紀子/ 鈴木 親彦/ 王 一凡
なお、この日本語訳の元のエッセイA Short Guide to the Digital_Humanitiesは、MIT pressより出版されたDigital_Humanities, by Anne Burdick, Johanna Drucker, Peter Lunenfeld, Todd Presner, Jeffrey Schnapp, MIT Press, 2012の一部〕

