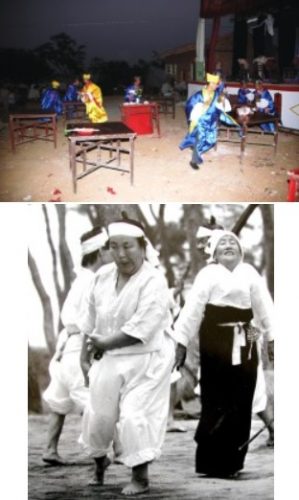目録
天の北半が晴れ風僅か

満足満足。1330。
空は……北半が晴れてる。南から北へ筋雲が襲いかかってる感じ。風は僅か。これは夕日は待たずに今を狙うべきか。出発しよう。
──とメモりながら、上甑トンボロの集落がちょっと面白過ぎました。順当に考えるなら砂州の上の仮屋を原風景にする家屋群のはずなんですけど──

「薗」というのが、里港南の武家集落(村∶村西・村東)に対する庶民集落の呼び名だった、と考えられてます。地図上、南から上・中・下の「薗」が並んでます。武家が南に住んでたからその方向が「上」だったのでしょう。
道の法則性が、ありそうで、ない。中・下の粗い北東-南西のラインが、上では急に途切れ、筆のドットが急に細かく変わる。国民宿舎跡と言われる里中学校、その北を流れる水路が何か関係している気もしますけど──読めません。

トンボロの丸石垣から長目の浜

個別の景観にも──劇的なものはありません。ただ何とものびやかな、印象的な家屋や間取りが多い。感じとしては沖縄家屋のそれなんですけど──そう主張する個別の根拠も薄い。

側溝も石垣もサラッと整備してあります。観光用と決めつけるほどでもないけれど、ドロドロに汚れ生活感たっぷり、という感じはしません。
なお、トンボロ西には浜。岩もあるけど夏には賑わうのでしょう。

丸石垣は、素人目にも確かに見事。6段のブロック塀がずっと集落内に続く。
丸石垣の道もありました。
角ばってない石を使わず、こんな長く、それなりに高い石壁を造れるのはハイスペックな技術だと感じます。

パティオらしき場所も。位置的には上薗の境付近ですけれど、中と上の境目のようにも見えます。従って推認できません…。

さて!そろそろトンボロは出たはずです。
1352、三叉路(→GM.)を過ぎて……え??
ええッ──!!!

かのこゆり咲く浜の道行き止まる
物理的に道がなくなってる。
でも……住民がゼロじゃないだろう?迂回路があるだろう?としばらく嗅ぎ回ったりスマホで調べたりした挙句──

三叉路でよく見ると迂回路を示してあるけど……これは多分、中甑から回って行くルート指しているはずです。自転車ではとてもとても。
でもだよ?そこまで大回りしなくたって、間道はあるんじゃないの?

見つけた。上記ルートなら行けるけど、この迂回路が海に出た地点で、ホントに工事が終わってるという保証はありません。電話でも出来るならかけてみたかったけど──電話番号の掲示もない。
ここを強行突破するのは……ものすごく危険に思えます。
無理ですね。
引き返す前に……長目の浜(方向)の画像を一枚。鯉幟が泳いでる。

薗上老人倶楽部前に「畜生碑」。一般的には牛魂碑として建てられるものでしょうか?
そのまま里集落を抜けてくと、たまたま「我夢」を通りました。昼メシを思い出して、ついつい一夜干しをまた買ってしまう。おばちゃんに「あんた、昨日もこれ買って……」と顔を覚えられてしまってた。一応「いえ一昨日ですよ」と訂正しておきましたけど──。

1414、ケイダストアー前に自転車を停める。
武家屋敷を歩いてみる。

曝された山田さんより百年前
真言宗大聖院。
柔和なお大師様像。
入口右手の表から見えない場所に荒熊大明神。祠は新しい。左右にお狐様、宇賀神の系統か?えらく凶暴な、もののけ姫の山犬みたいな面構えの狐様です。

1426、里(中町馬場)遺跡。
馬場の遺跡じゃなく、縄文前期からの集落遺跡だという。埋葬跡も発見されたんだとか。
縄文時代末から弥生時代前期にかけて間断なく遺物が認められ,南九州だけでなく九州南半の弥生時代成立過程を考えるうえでの重要遺跡といえる。弥生時代早期から前期の土器の大半は,北部九州の有明海沿岸部から薩摩半島に至る地域に共通した特徴をもつ。特に前期で主体となる甕は,口縁部の断面が三角形を呈するもので,早期の刻目突帯文土器の系統をひく(第3図16〜20) 。これは北部九州南部から薩摩半島を中心として分布する亀ノ甲タイプと呼ばれるものにあたる。一方,北部九州北半から西日本に広く分布する口縁部断面が孫の手状に外反する甕はごく少量見られるにすぎない(第3図21•22) 。本遺跡の土器は黒雲母を多く含むという特徴があるが,後者はそれが見られないため,搬入品の可能性がある。なお,弥生時代成立期前後に南西諸島系の土器が出土する遺跡は九州では稀有である。〔後掲鹿児島県上野原縄文の森〕

1430、武家屋敷通りどん詰まり。どこだろう,愛宕神社は?──でも愛宕社に行きつけぬまま、寺を見つけてしまってます。神宮寺なら寺最奥に神社がある可能性はあるか?……と入ってみてます。
1431、旭宝山西昌寺跡(西願寺)。
日置市のお坊さんから送られた狂歌が碑にしてある。
さらに墓奥。「山田静治有秀の墓(一向宗取り締まりの役人)」という案内板。

本村で一向宗を信仰していたのは主として農漁民であり、講をつくり「隠れ山」などで仏をまつり、しられないように念仏を唱え信仰を続けていた。これを「隠れ念仏」と言う。
出水郡郷士山田静治有秀は甑島の取り締まりに派遣され、厳しく取り締まりに当たっていたが、慶応二年(1866年)に病没した。
彼の実直で余りにも非情な仕事振りは、人々の憎しみをかい、病になり、苦しみながら死んだと伝えられている。

その墓がなぜここに?──と考えると……ここは墓地の一番隅っこ。しかも時代は幕末の混乱期。死後も地元民によって半永久的な晒し者になっている、と考えていいのでしょう。つまり、かなり恨まれた人です。合掌。
さてまだ階段はあるけど……仮にこれが愛宕神社の参道としても荒れ過ぎてます。戻る。

戻り道、安永年代の墓石を見つける。安永は1772〜1781年、先の山田さんより百年古い。
あく巻の皮十枚は三百円

ケケイダストアー。用件としては一味唐辛子を求めたんだけど──え?
あく巻の皮10枚298円?そんなん売れるの?──下記が画像ですけど、

1514一応、亀城に寄る。
亀城は、鶴城とあわせて亀鶴(きかく)城という。高所から見るとその形が、鶴と亀に似ているのでこの名がある。鶴城跡はこの地より南東二百メートルの丘にあり「古城」(ふいじょう)ともいう。
亀鶴城は、もと甑隼人の城であったといわれる。[案内板]
城跡らしきものも祠も何もない。慰霊碑はあるけど関係ない。地元の感情が読めない立地です。

展望台(→GM.)からトンボロを見下ろす。
やはりそうだ。──西半だけが古い。
港に近い側を開発したから──にしては極端過ぎる。なぜでしょう。
しかもかなりくっきり区切られてる。支所西側の道の延長らしい。そこに道は伸びてるけれど、住所上の色分けでもない(里+4桁表示、一桁目の数字の区分でもない)。
さっき通った辺りなんだけど……仕方ない。もう一度縦断してみるか!
GM.(経路)

1540。その境界ラインは、支所からまっすぐではない。郵便局の東側の道らしい。
1544。薗中集会所。

トンボロに背骨はあるか イトラッキョウ

Ⅰ547、薩摩川内市消防団里分団北部。左手に薗下自治公民館。この前が不規則なパティオ状になってる。これ……元の海岸線か?
パティオというか変則交差というか、とにかく北東に歩く。さっきの道(→丸石垣の道)です。やはり、道の景観そのものは何ともとりとめがない。
1551、あまり新たな発見はないまま北端まで来てしまいました。集落はばたりと途絶えます。ここに岩造りの壇。新しいしコンクリで,GM.上この北には墓地が見えるからおそらく墓所。ここからの道は普通林道白瀬鼻線と書いてある。
分からない。取っ付き所がない。この集落は一体何でしょう?

1557、一つ西のラインを帰る。このラインが左右よりわずかに高い。つまりトンボロの「分水嶺」みたいなラインになります。
と言っても砂州なんだから、実際に水脈があるとは思えません。単なる微高地のはずです。
きびなごの一夜干しには唐辛子

なるほど。この道から西の道は湾曲が強い。なのにさっきまでの東の道はまっすぐ。
つまりこの尾根道の左右までは都市計画がないまま集落が造られたけれど、東半分は都市計画が先にあった。江戸期に造られた地域なのではないでしょうか。──そんな時間的な分化がなぜ起こり得たのか不詳ですけど、あり得る想像は、東半分に浅い自然の防風林のようなベルトがあり、西半分集落はそれに隠れるように形成された、という展開です。ただ全く根拠はありません。

1616、里港でタバコ。消化不良ではありますけど、自転車の返却時間が近づきました。
ケイダストアーでは一味唐辛子を購入してます。教え通り一夜干しに一味を振りかけると──凄絶な旨さに変貌いたしました!
酒よりお茶が合う。たまたま川内駅で手に入れた白茶があったので……これは素晴らしい「夕食」となりました。

■レポ:上甑に係る断章三編
以下は、他資料と連結点が見つからない、単発に終わった資料です。今後甑島を訪れ、または考えられる方にお伝えするため掲げておきますけど、趣旨的に特殊なものが多いです。
小島∶「いとこどうしか 似てござる」
島じゃ御縁節 串木野じゃ六調子
名所鹿児島じゃ しょんが節
島の御縁じよと 地方の節は
いとこどうしか 似てござる
この二つの歌詞を味わってみると,島民が御縁節を持っていることを自慢に思い,島の御縁節と鹿児島の歌とは,従兄弟同志のように似ていると唄って,おたがいに縁につながることを強調しているのは興味がある。
藺牟田瀬戸わきや 白波絶えな
わしが胸には 苦は絶えな
一里二里なら てんまでかよう
五里とはなれりや 通われな
下甑にや三十日 平良にや二十日
折角小島にや 潮がかり
(略)小島は平良の港が開かれる以前は,甑島唯一の台風の避難所であり,また上り下りの舟の寄港地で,港女もいて繁昌したといわれる。
[後掲郷土史編集委員会「郷土史 上甑村平良」平良小中学校PTA会長,昭45。以下「郷土史」という。p19御縁節]
海域を縦横無尽に行き交った船が目に見えるような口説ですけど、最後段「折角小島にや 潮がかり」に注目してみましょう。郷土史は「平良の港」以前には「小島」(→GM.)が避風地で、それも「甑島唯一」だったと記します。根拠は不詳ながら、地形的には不思議のない位置です。
さらにwiki(上甑町小島)は「堅町には住吉神社があり、中村戸兵衛という落人が住吉之神を神底に祀ったものを、元禄年中に神底から堅町から遷座した」[9][10]と記します。
[10]住吉神社 – 鹿児島県神社庁 2011年11月9日閲覧。〘▶現在リンク切〙
「神底」がよく分からんのですけど、甑島大明神の御神体というAI回答も(やはり根拠未詳ながら)あり……それを信じるなら、甑島の語源になっている大明神は元々「小島」時代に形成された可能性があるのです。
この「小島」は「おしま」と読みます。これについて同じくwikiは、次のように記します。
「上甑村郷土誌」によれば、現在は埋め立てられ陸地となっているが、小島(こじま)と呼ばれる島がかつてあり、その小島に由来していると推測してされている。また発音については両者を混同しないように区別したものではないかと記述されている[11]。〔wiki/上甑町小島/地理/地名の由来〕
そうだとすれば

都落∶私は信太の森に居る
同じ御縁節の中で、上甑誌は次の箇所に着目しています。
◯ 御縁あるなら 尋ねておじゃれ
わたしやしのだの 森 にいる
◯ わしが体は 山から山で
花の都にゃ 縁がない
王朝時代の末期,源平の戦に於て壇浦で破れた平家の残党は(ママ),相当の人数を以て此の島に落ち延びたらしい。現今は無論他姓を名乗っているが,「信太の森」といったような詞は,ぼつ然としてこういう辺地の孤島に発生する筈がないように思うからである。多少の心得のある者でなくては出てこない句である「信太の森」は歌の名所で,和泉の国信太村にあり,信太郎神社の西方約十町ばかりの地に大樟樹があり,土地の人々は「信太の森」と呼ぶという。明神様の旧地だといい,樹下に狐が棲んでいるという{。}「源氏物語」若葉の項に
「しのだのもりを道しるべにて詣で給ふ云々」
とあり「枕草子」にも
「森は……こがらしの森 しのだの森云々」とあり(略)それを其のまま遠くこの島へ平家の残党と共に移入したのであろう。「花の都にゃ縁がない」などという詞もうなづけるのである。[後掲上甑誌]p263 ※傍点∶引用者
正確に言えば「平家の残党」たる真実味は疑わしいかもしれません。でも、和歌の世界観の場所≒近畿中央からの人間集団の移入が、源平争乱期にあったことは、少なくとも九州の他地方よりは確からしいと思っていいでしょう。もちろんその姿は、具体にはまるで見えてきませんけど──。

引導場∶霊は目を回し帰れない
上記「小島」の葬制には、次のような変わったものがあるという。「引導を渡す」葬制は成語になるほどメジャーですけど、そのための専用台があるのは珍しい。
三,葬儀
もとは葬儀は墓地で営まれた。墓地にはインドウバ(引導場)という石の台があって,坊さんの読経や会葬者の焼香があった。小島では棺を置く前に,棺を三回まわした。これは死者の霊が家に帰らないように,家の方角を失なわせるためであろう。[後掲上甑村郷土誌編集委員会「上甑村郷土誌」上甑村,昭50。以下「上甑誌」という。p189]
浄土真宗は、信者ば死後必ず浄土に行くという教えですから、霊は「引導」される必要がないとされます。逆に言えば、引導場の存在は、霊は「迷う」ものであるという観念が強い、墓場では常に霊が迷っている、と観念されていることを意味します。これは福建由来の海民文化と思われる「施餓鬼」(普度)の感覚と底通しそうです。
でもそれが、小島にとどまり拡大していないのも、また事実なのです。