目録
新大工 片渕からの春徳寺
GM.(経路)

正午を迎える。
こちらが新大工町4、北側が片淵一丁目7の十字路。これを北へ進みます。と言っても特に計画性はなく、この先の石垣に惹かれて入ったのですが……。

ただしっくい部が少し黄ばんでるだけで、道は割と普通。ただ、家屋はなぜか妙にギラつくものが多い。


道なりに右へ曲がる。ad.片淵一丁目9(→GM.)。東の高みに寺院らしき建築が見えます。──春徳寺、なのか?あんなに高いところに?
城の古址自体が標高105m(前掲地図参照)ですから、高度が高いわけじゃない。水平距離に対し傾斜が激しいのです。
1210、進む。
夫婦の川のとっぽ水

駐車場、そしてデイサービスと面白くない郊外の道。
T字。Top24パーキング夫婦川(→GM.)。ad.夫婦川2の横に東への細道がある。これに入ってみようか。


さらにT字。ここは位置からして……一度南へ回っておこう。右折南行。
東海の墓を示す案内板が階段を示します。その手前に「トッポ水」(→GM.)という泉の祠。これを源泉とするのが雌川、春徳寺下の斎道寺泉を雄川と呼び、総称して夫婦川……と案内板にある。中国語訳は「金刚杵圣水」。祠はありません。

三界萬霊一度は断首
道はそこから階段になる。1223。
真上に夫婦川町公民館。その脇が夫婦川観音堂。長崎88か所の29番寺で,前後は75)華嶽山春徳寺、56)夫婦川天寿庵、だという。

右右に三柱の像。
なぜか皆首をかしげてる。これは多分……首を折られたのをくっつけてるらしい。廃仏毀釈か大村キリシタン時代か。真ん中の、これだけは辛うじて割られていない掘り抜き像ははっきり女性的だが,書かれている地蔵ではなかろう。
何の像でしょうか?

1235。寺の裏に一段段差。階段は10mほど等高線の平面をとってから、Y字路になりました。右手へ東行。
ad.片淵二丁目14から左が夫婦川12、右は4。
曲がりくねる道から再び等高線の道へ。三界萬霊塔。仏像18、やはりその多くは一度断首された跡あり。

1246。東海の墓の矢印がやっと右、つまり東を向きました。
1247、到達。1670-80頃の建立とあります。
東海さんの墓普請のごたる

実はこの時、なぜ東海墓を目指したのか、全くメモしてないし、記憶もしてません。何も調べてなかったから、これ以上特に何も見てません。そこで今初めて調べたんですけど──

昭和初年に春德寺本堂裏改修時、その床下から大理石板が見つかります。教会の祭壇に使われたものと推測されました〔後掲travelnagasaki〕。
それ以前から寺の井戸は、トードス・オス・サントス教会の時代に造られたと言われてきました。伝えでは──大村純忠の家臣でキリシタン・長崎甚左衛門がイエズス会のアルメイダに与えた土地に、1569年ビレラ神父により建設。何と長崎最初の教会だといいます。これが禁教令を受け建て替えられたのが春德寺とされます。現在、この井戸と大理石板のみが、この知られざる古教会の痕跡とされてます。──伝えと言っても、井戸に付された「外道井」(≒悪魔の井戸)の由来話程度でしょう。教会関係者や信徒がどうなったのか、一切の情報は欠損してます。 ※井戸の拝観は要事前予約
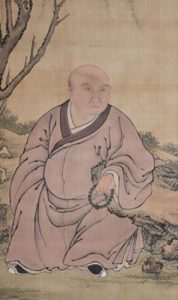
「東海」とは、唐通事の一族「東海氏」で、その3代目以降の墓地がここです。鉅鹿家魏之琰兄弟の墓(県指定史跡∶長崎市西山町二丁目36番地)と並ぶ、長崎所在の代表的中国式墳墓〔後掲長崎市〕。
東海氏の祖は中国・浙江省紹興府の人で徐(じょ)敬(けい)雲(うん)。元和3年(1617)長崎に渡来、酒屋町に居住。夫人は大村の人。長男・徐(じょ)徳(とく)政(せい)が2代目で、東海徳左衛門と名乗った。徳左衛門は唐小通事となり、のち目付役となる。慶安2年(1649)に父・徐敬雲が死去、万治元年(1658)には母が死去する。この墓は2代徳左衛門が両親のために造営したもので、10数年の歳月を要し、延宝5年(1677)には竣工したという。〔前掲長崎県〕

つまり、祖先の死霊による王国をこの斜面に展開させている訳です。ただし、この造立者たる2代徳左衛門の墓は存在せず〔後掲長崎市〕、どうやら最大の謎とされています。
全体の平面は五輪塔の形を示すが、意図的に計画されたかどうかは不明。周壁・床面は石を畳み、石柱・扶壁・石欄その他は文字・植物・動物などを彫刻し、獅子頭の眼には金箔を張って、これが陽光に輝くのが港から望見されたという。最奥に徐敬雲夫妻の墓碑があり(略)〔後掲長崎県〕
「獅子頭の眼」の金箔が入港船から見えたとすれば、それは港を向いていた訳です。この「獅子頭」がどこにどういう形であるのか、訪問時は気にしてなかったので分かりません。
この墓造りが完成までに長い年月を要したことから、長崎には、物事が遅々として進まないことを例えて言う「東海さんの墓普請のごたる」という表現があるそうです〔後掲長崎新聞〕。
出れない墓地のベーロン

さて?ここからどう……東へ出ればいいんだろ?
墓地内を抜けるしかなさそうですけど──なんだこの道筋は?全然抜けれんぞ?
墓域が完全に城砦を成していて、正面以外に抜け道がないのです。


ようやく、日本人用の墓地に入り直しました。脇道がないのは中国人墓地だけのはずです。
まあここもそれなりに迷路だったけど……何とか抜けれました。
この上が「城の古阯」のはずだけど?でも今出た道は、再び西に回り込んでる。城へ向かうなら、まっすぐか東から入る必要があるのです。

城の古址シリーズ開幕
先へ行くと長崎美容専門学校?それ以外の山手への道がない?
──鳴滝二丁目、城の古址ハイツの辺りからシーボルト宅跡の鳴滝本流側へは、西と同じく段差があるようで、直接は行けません。つまり──

──公道としては南のシーボルト通りから回って行くしかありません。でもこの初回は、そうは言っても私道の一本位は……と高をくくっていたのです。
アパートからタイ語の嬌声。


城の古址については、この回の最終日、つまり二日後に再挑戦。さらに二年後、万全を期して、ようやく縦断することができました。──という長々とこだわり続けることになります。続編としてご笑覧頂ければ……。
2022.07→010-d/城の古址(表)
010-e/城の古址(裏)
2023.07→
025-2/矢ノ平稲荷∶鳴滝方面からの進入路探索
2024.08→
010-f/城の古址(真裏)
~(m–)m 本編の行程 m(–m)~
GM.(経路:地蔵堂
〜城の古址北入口)

観音堂から中之橋の現世へ

1321、桜馬場町観音堂。
1324、中之橋。
──とようやく下界に帰って参りました。……という気分に、城の古址方面に入った後は、いつも思うことになります。


西洋菓子「樹」に久しぶりに立ち寄る。
1332、電停・新中川町から乗車。
電停向こうに春徳寺奥の高みを確認する。ここからの見かけは単に、小さな丘、というだけです。
この丘が……そんなに重要な意味を持ったのでしょうか?
城の古址が何なのか誰も知らない

この、諏訪神社より上の長崎は、今んとこどうもコッ酷い長崎です。
完璧以上な準備なしに迂闊にホールドをつかむと……ヒドい目に遭います。ぜんぜん取り付けない。旅行では未知の事態に臨機応変するのが普通ですけど、長崎のこの古層エリアはその場で全く対処できません。それが凄い。
──次の図は、夜に思い起こしつつ地図を弄った結果、何とか地理的に見つけた原因把握です。

最後に、東海の墓を起点にした「城の古址」の記述を掲げておきます。しかしこれを見ても──
「東海の墓」の百メートルほど北東にある西向き斜面には、幅四十・五十メートル、奥行き十五・二十メートルの凹地があって、片側は高さ十メートルほどの垂直な崖になっている。ここが江戸時代に石材を切り出した採石場あとのひとつである。現在はうっそうとした森に包まれていて、外からはまったくみえない。しかし、西(山頂に向かって左側)のほうにまわりこむ小道があるので、これにそって歩いていけば、かんたんになかまではいることができる。そのすぐ裏山が「城の古址」(しろのこし)である。(続)〔布袋厚著「長崎石物語 石が語る長崎の生いたち」長崎文献社2005年刊の52〜55頁←後掲みさき道人〕
上記みさき道人の前掲出典画像によると、この引用文の続きに次の一文がありました。
(続)この山には「トードス・オス・サントス」の音に由来する「
唐渡山 」という古い別名がある。〔後掲同上〕
とーどすおすさんとすの教会
又、同布袋書には「トードス・オス・サントス」は、ポルトガル語で「諸聖人」の意とあります(p52)。
これを含めて読むと、面白くも益々訳が分からなくなるのが次のコトバンクの文章です。
城 山(一〇一・八メートル)に築かれた中世の山城の跡。桜馬場 城とも記され(木村家覚書)、跡地は城の古址 (城ノ越)ともいう。長崎氏の居城であった。戦国期、長崎氏一四代の甚左衛門純景は天正元年(一五七三)・同六年・同七年・同八年と深堀純賢による数次の攻撃を受けたとされ、天正元年には夜半の満潮を利用して六〇艘の船で来襲、長崎の殿の城下まで焼払い、城砦の下手の家々と宣教師らがもっていた諸聖人の教会も焼かれたという(フロイス「日本史」)。〔日本歴史地名大系 「鶴城跡」 ←コトバンク/鶴城跡〕

最後に記される「諸聖人の教会」が、ほぼ間違いなく長崎初の教会「トードス・オス・サントス」です。つまりこの伝によると、一般に禁教令で破壊されたと言われるこの教会は、長崎甚左衛門純景の宿敵・深堀純賢の1570年代の連続攻撃によって焼かれたことになるのです。
また、諏訪神社南西付近の現地名「桜町」は、桜馬場城と関係を持つ、例えば何か他の同一語源から派生したものである可能性があります。
斯くの如く、城の古址に関しては由来も何も全てが霧の中で流転しています。何かが確定される日が来るのでしょうか?



